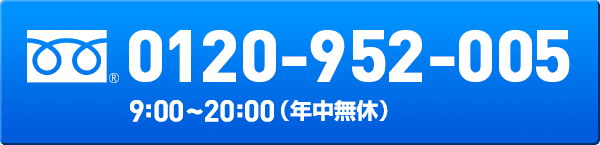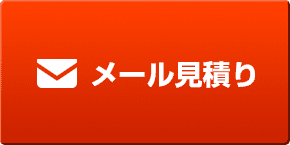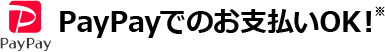建設発生土(けんちくはっせいど)
建設発生土の不適切な処理が引き起こす最悪の事態
建設発生土とは、建設工事などで発生した土砂のことで、残土とも呼ばれます。国土交通省は「建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料」の中で、「自らの工事内や他の建設工事、又は建設工事以外の用途において有効に利用されることが望ましいが、一部の建設発生土については利用先が見つからず、その他の受入地に搬入されている。」と記しています。その上で、「一部の悪質な受入地においては、無許可又は許可条件に違反した行為が行われ、過去には、崩落に至る事案も発生している。」と警笛を鳴らしています。
実際に、台風などで地盤が緩んだ際、別の地域の工事現場から運び込まれた建設残土が原因で土砂崩れを起こし、住宅地で崩落事故が起きるなど、建設発生土による崩落事案が後を絶たず、問題は深刻化しています。
その背景としては、工事の現場で建設副産物として出る土は、混入物が混ざっており、産業廃棄物に該当するものを取り除かなければいけないという手間がかかるという点も挙げられます。
有効利用が求められる建設発生土、その区分とは
発生土は、埋め立てや盛土の材料として土地造成などに利用できる有用な再生資源であり、その適正な利用の促進を図ることを目的に、土質の区分基準が設けられています。
*第1種建設発生土 「砂、礫及びこれらに準ずるもの」
*第2種建設発生土 「砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの」
*第3種建設発生土 「通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの」
*第4種建設発生土 「粘性土及びこれに準ずるもの(第3種建設発生土を除く)」
*泥土
この基準に基づき、例えば第1種は工作物の埋め戻し材料や土木構造物の裏込材、道路盛土材料に、第2種は土木構造物の裏込材、道路盛土材料、第3種は道路路体用盛土材料や河川築堤材料、水面埋め立て用材料など、主な利用用途に合わせて再利用に務める必要があります。
建設発生土は廃棄物処理法の適用から除外されていますが、その処理による影響の大きさから、各自治体では土砂条例を制定し、対策を講じています。
また、建設発生土の有効利用を促進する取り組みや、建設発生土のリサイクルプラント、ストックヤードの設置・認定などの取り組みも広がっています。
さらに、建設発生土を工事現場から搬出する際は、情報の収集・提供を行うことで他の建設工事での利用を促進する、一定量以上の建設発生土を搬出する場合は、再生資源利用促進計画を作成することなどが求められています。