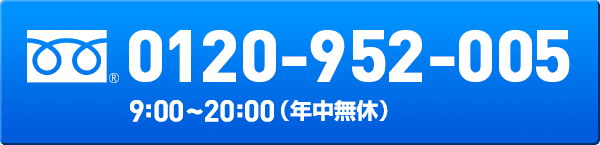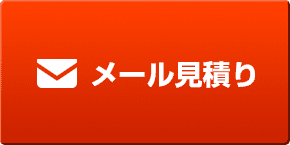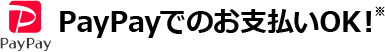バイオマス(ばいおます)
バイオマス=Biomassとは
バイオマスとは、再生可能な生物由来の有機性の資源で、化石燃料を省いた物を指します。使い続ければ枯渇してしまう石油や石炭、天然エネルギーといった化石燃料とは異なり、バイオマスは生物が光合成によって、太陽エネルギーを使って水と二酸化炭素から生成した有機物。生命と太陽エネルギーがある限り、持続可能な資源です。循環型社会の形成にも、バイオマスエネルギーは欠くことのできない重要な資源として利活用の拡大が期待されています。
バイオマス資源には、主に紙や動物の死骸・ふん尿、生ごみなどの廃棄物系バイオマス、木材や稲わらなどの未利用バイオマス、さとうきびやとうもろこしなどの資源作物があります。これらの資源を燃料にして電力を得ることを「バイオマス発電」と言います。
エコな電力供給「バイオマス発電」の方法とは
バイオマス発電には、燃料となる資源によって、大きく3つの方法があります。例えば、間伐材や可燃性ごみは、燃料を直接燃やす「直接燃焼方式」。加熱して発生したガスを燃焼して発電させる「熱分解ガス化方式」も一般的です。また、家畜のふん尿や生ごみなどは、発酵させてメタンなどのバイオガスを発生させる「生物化学的ガス方式」で発電が行われます。
燃料を燃やすと、二酸化炭素の発生が懸念されますが、バイオマスを燃焼させた際に放出される二酸化炭素は、生物の光合成により大気中から吸収した二酸化炭素であるため、新たな二酸化炭素を大気中に発生させることはなく、地球温暖化の防止にもつながるクリーンな発電方法です。また、使い続ければ枯渇してしまう化石資源とは異なり、資源を生み出すエネルギー源はどれも再生可能。バイオマスは再生可能なエネルギー源とされています。
さらに、太陽光や風力などの自然環境に依るものとは異なり、燃料が確保できれば安定した発電量を得ることができるという点も大きなメリットです。地理的な自由度も高く、燃料調達が可能な場所の近くに発電所を設置すれば、エネルギーの地産地消、地域の活性化につなげることも可能です。
具体的な事例としては、林業や製材業などの木材産業が盛んな大分県日田市の、隣地残材や未利用間伐材などを利用した発電所「グリーン発電大分」や、下水処理過程で発生する汚泥、生ごみなどを活用した愛知県の「豊橋市バイオマス利活用センター」などが挙げられます。